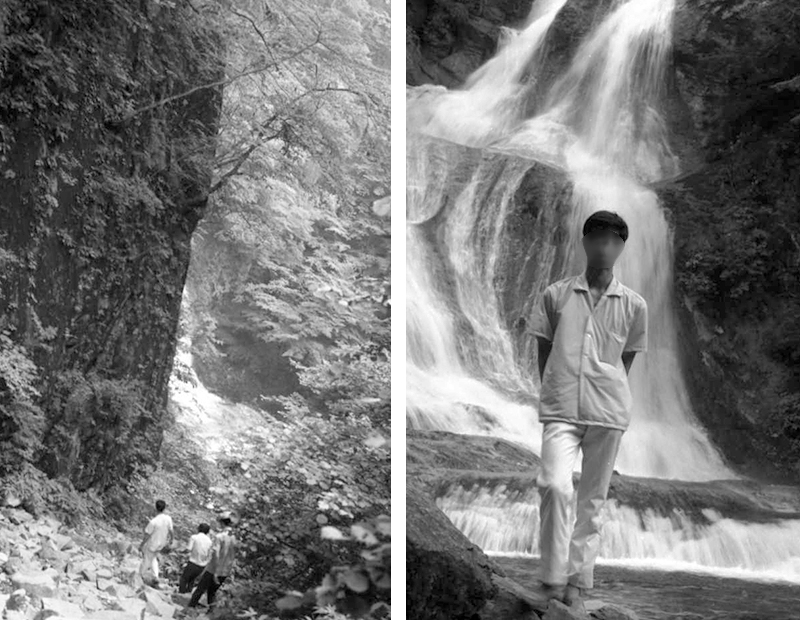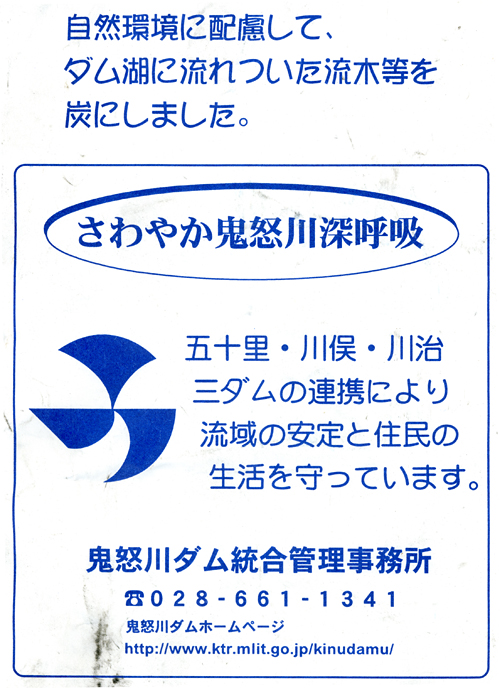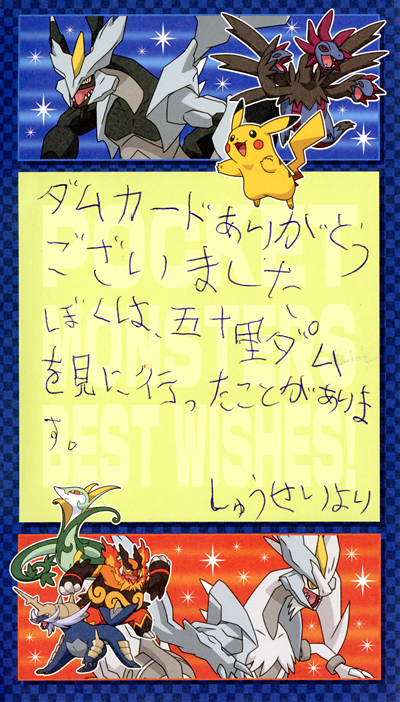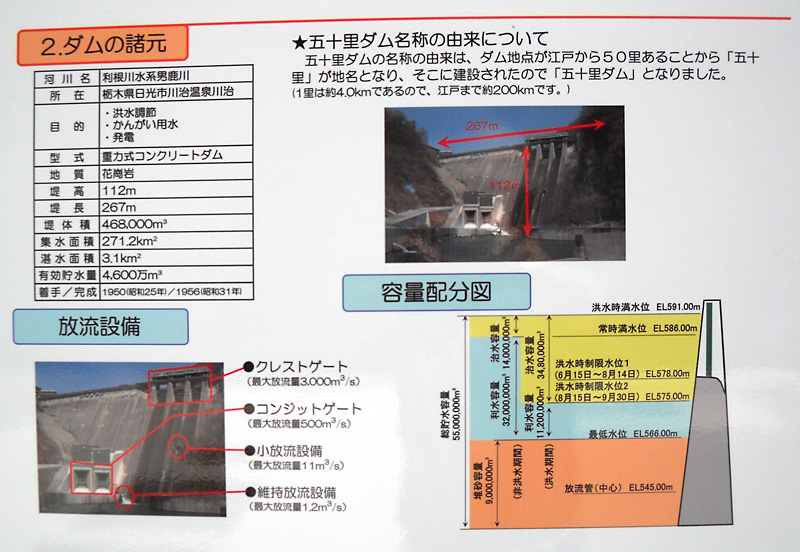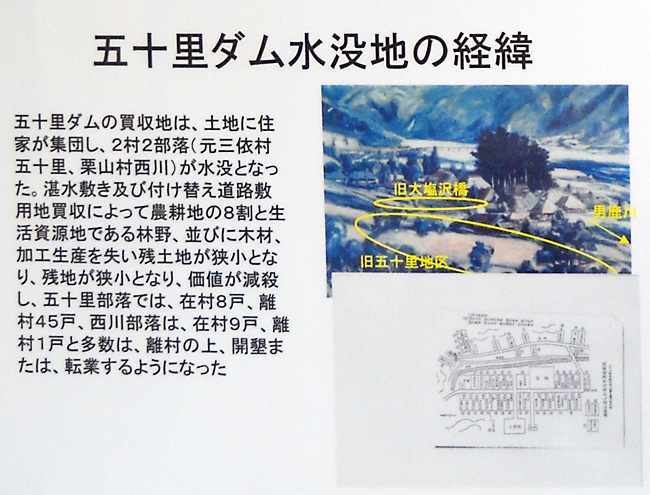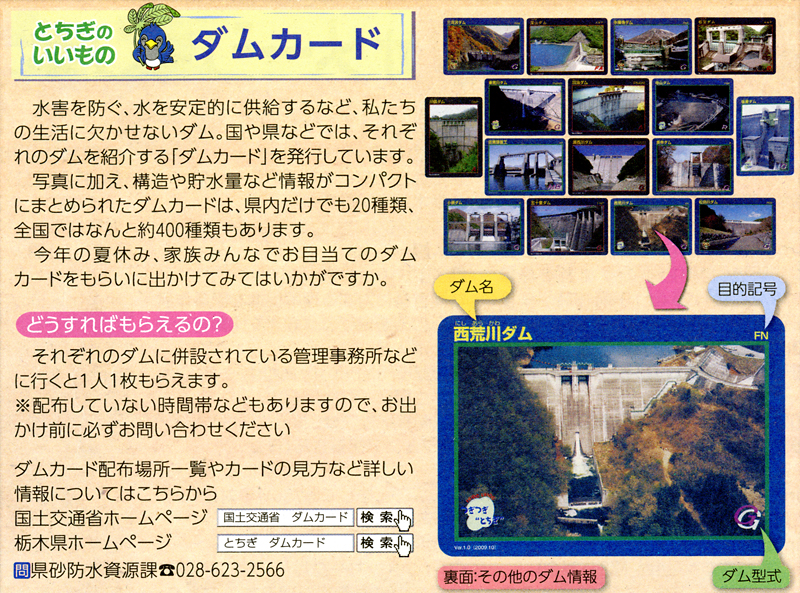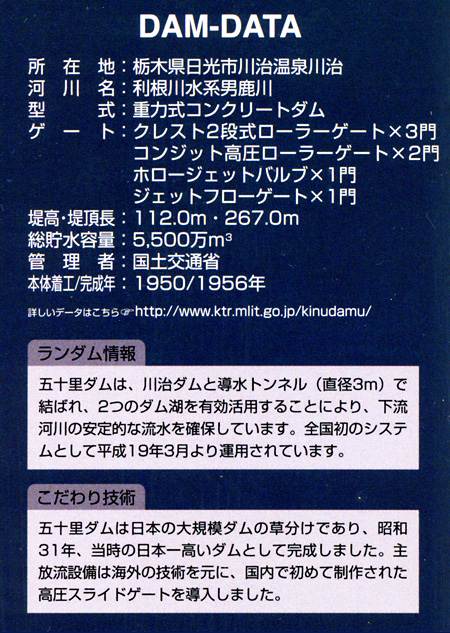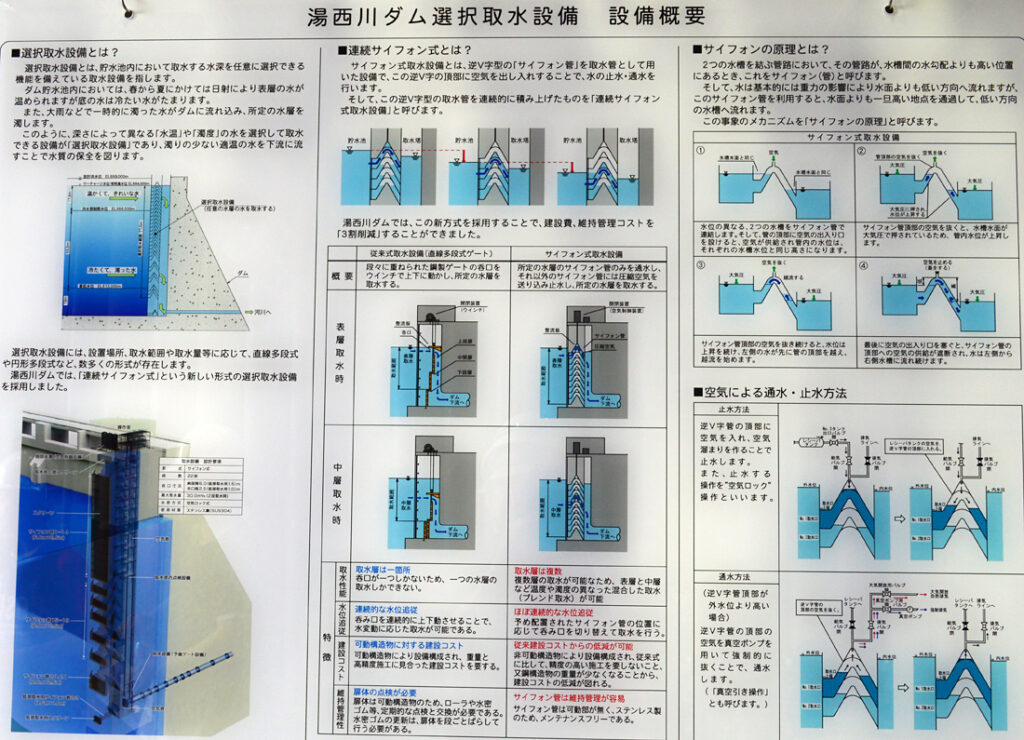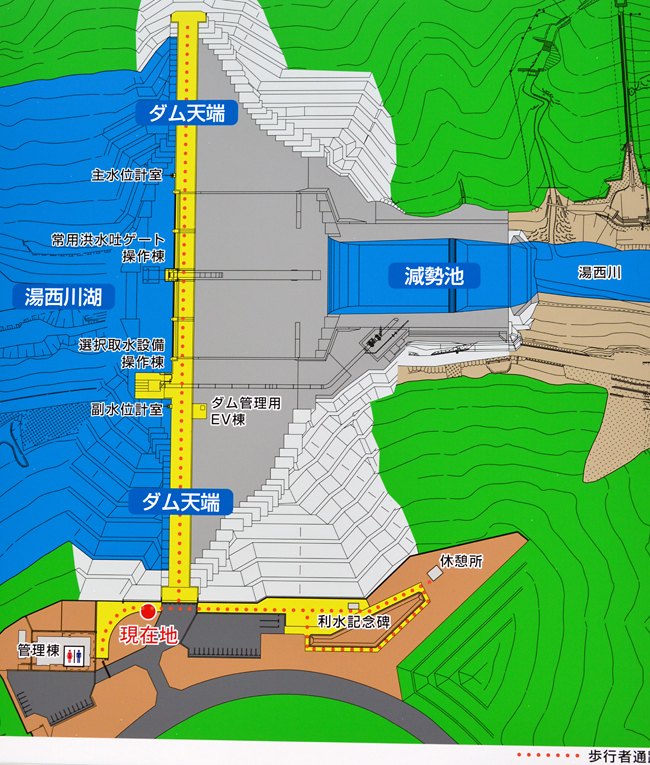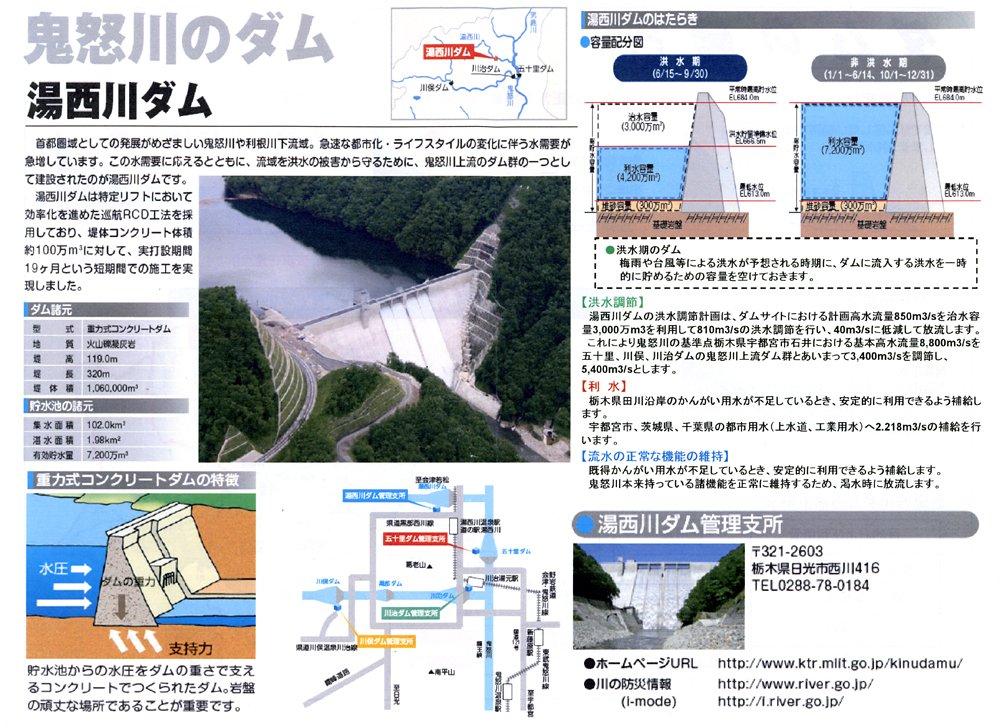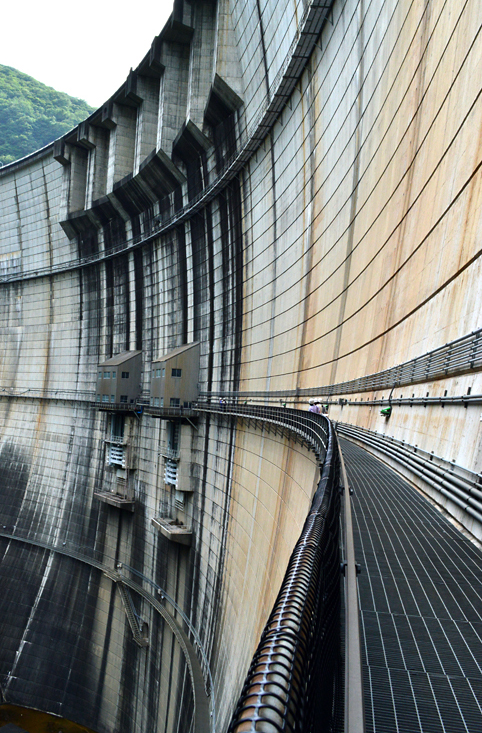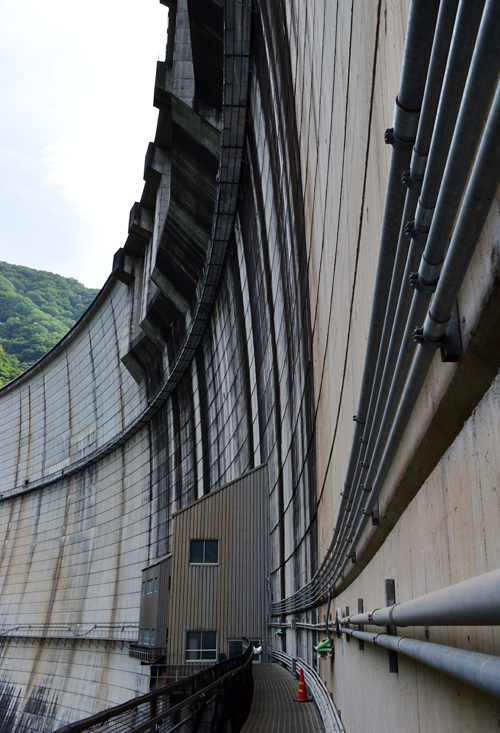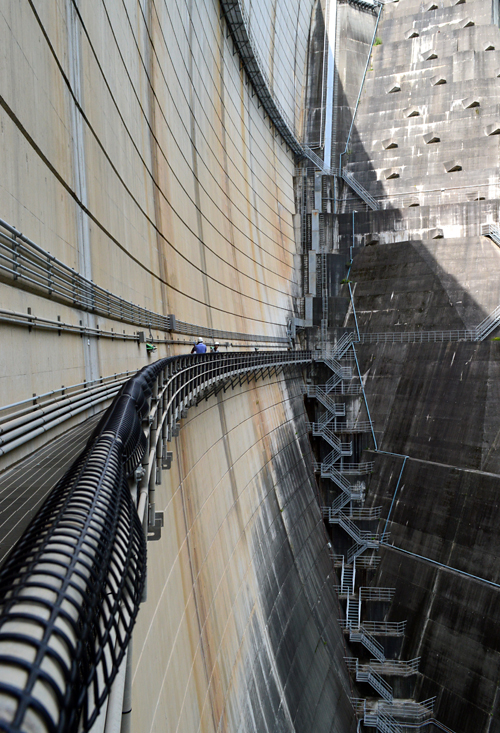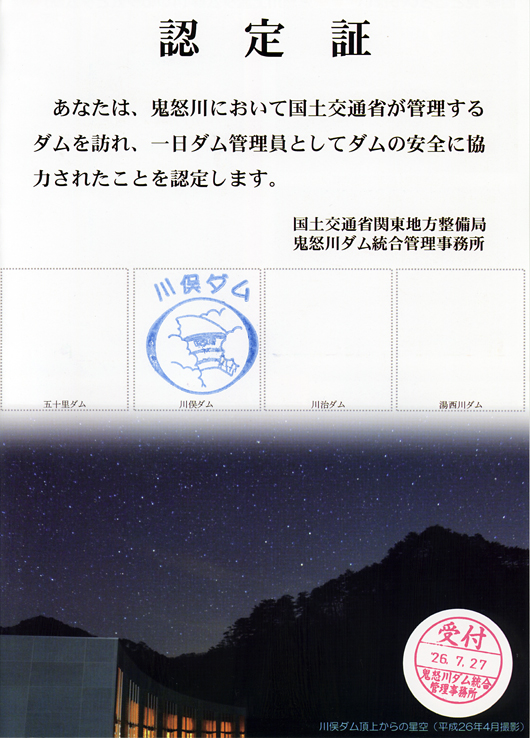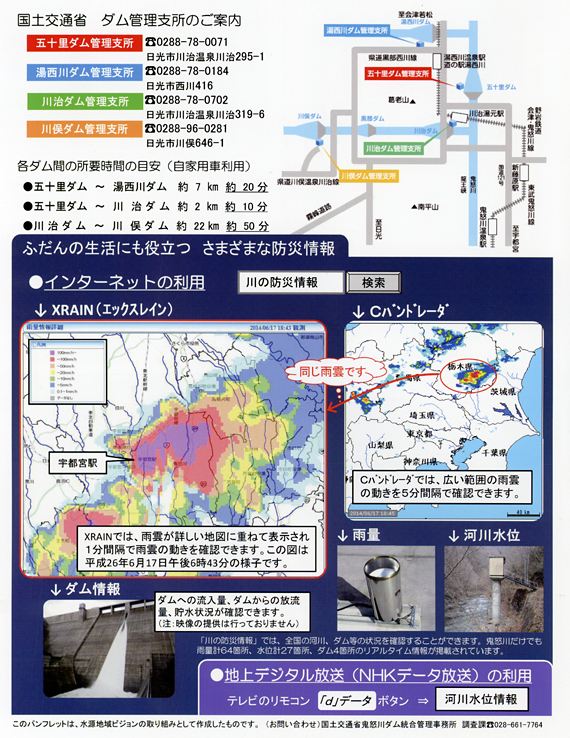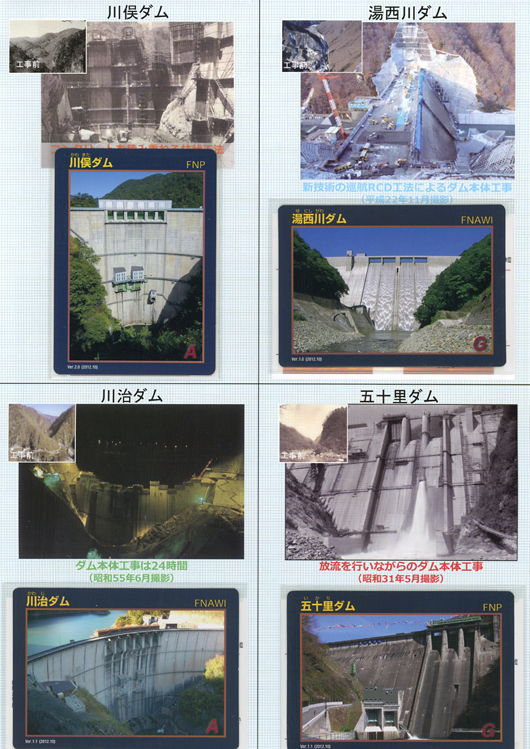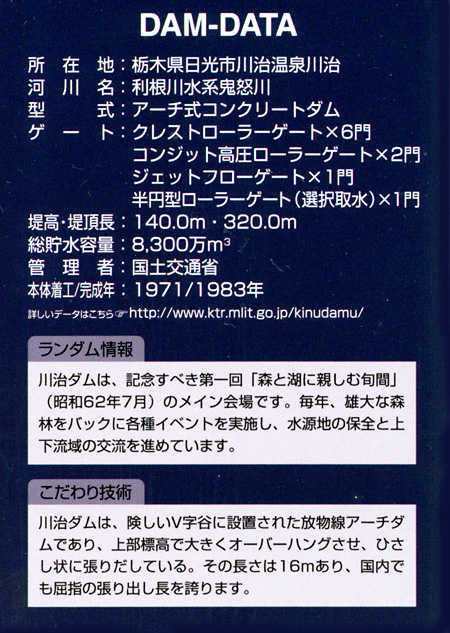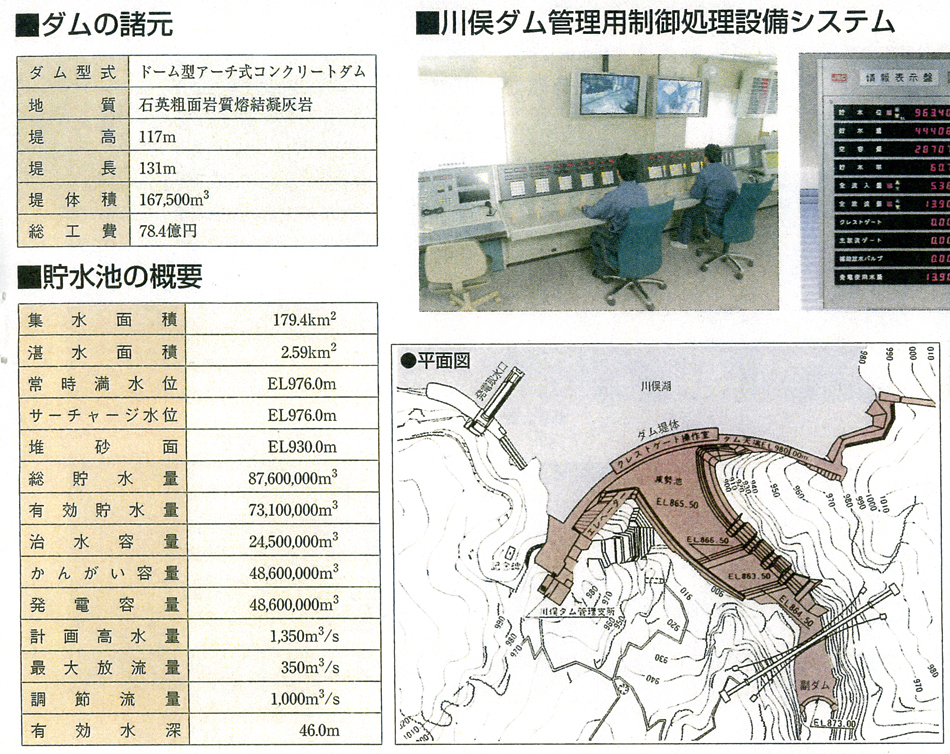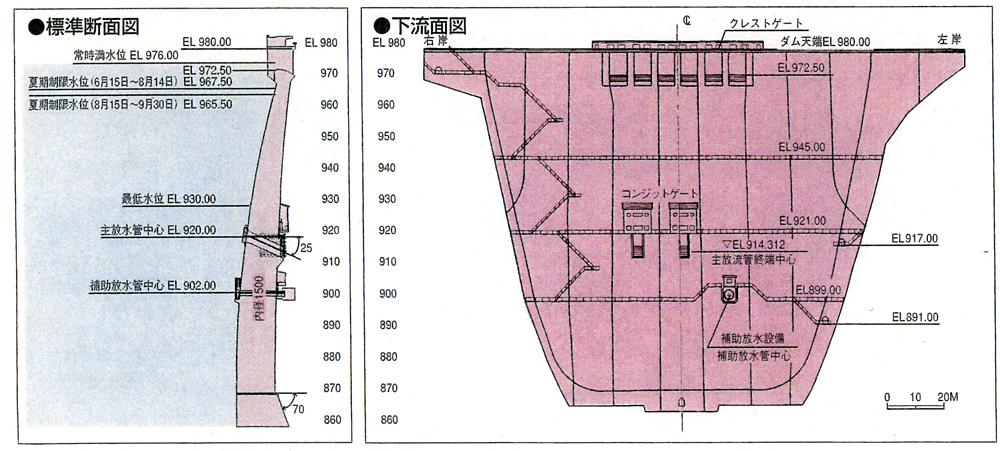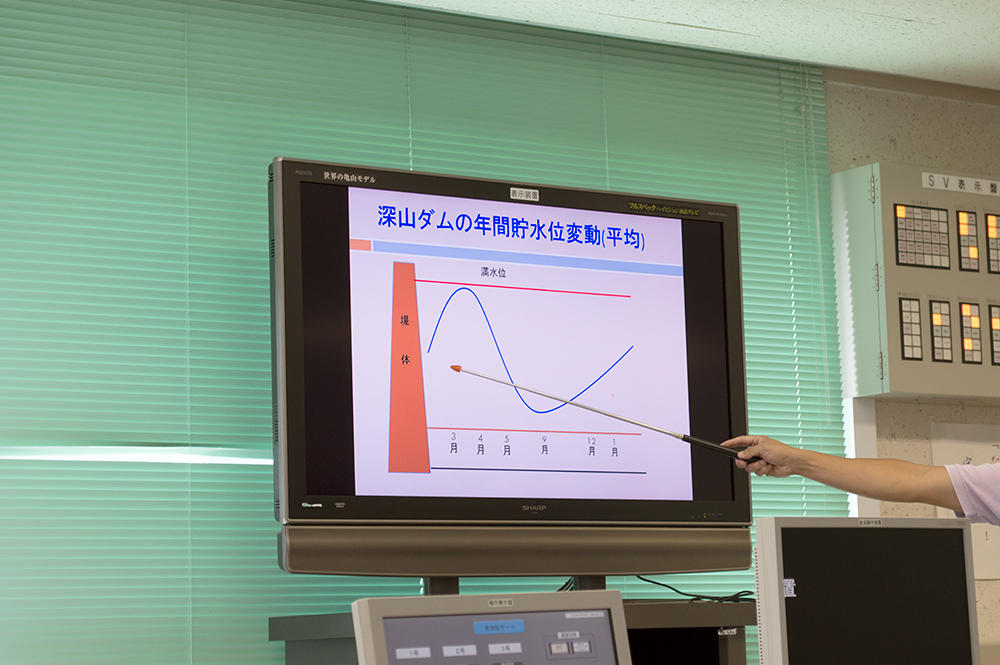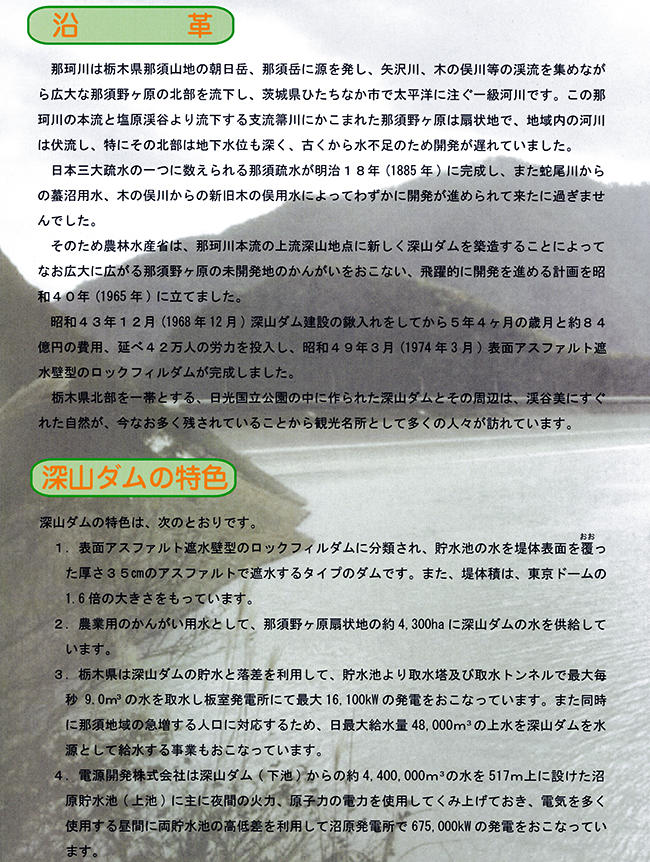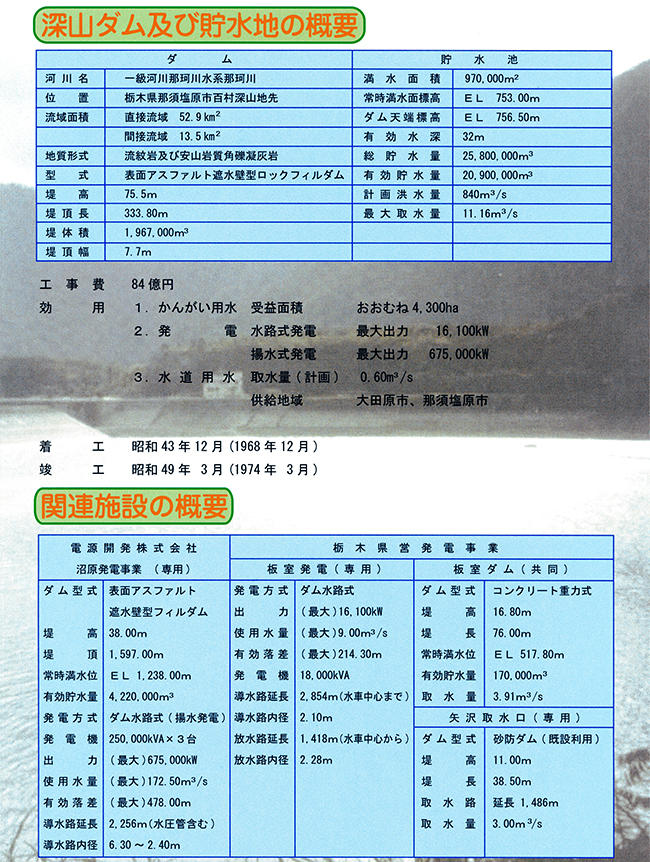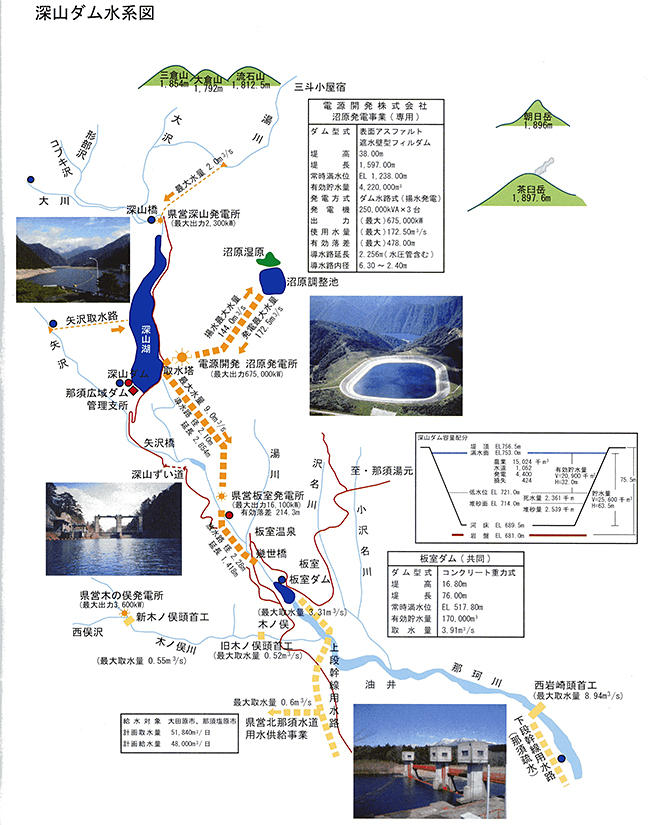第6回壬生町ゆうがおマラソン大会が壬生総合公園陸上競技場で開催されました。
師走に入って最初の日曜日とあって会場内は満杯でした。
最高の天気に恵まれ総合公園内は多くの人々で賑わっていました。
やはり、お目当てはシドニー五輪女子マラソン金メダリストの高橋尚子さんです。
今回もゲストランナーとして招かれていました。


私も、高橋尚子さんの写真を撮ろうとFINISH付近で待ち構えていました。
スマフォで数枚撮りましたがなかなか良い写真が撮れず、下右の写真がベストショットでした。
壬生町ゆうがおマラソン大会は第1回から見てますが高橋尚子さんのスリムな体型は殆ど変わっていませんでした。
この大会には、私の甥っ子も参加していました。


撮影日 2017年12月
投稿日 2017年12月
※ 壬生町合併70周年記念 第14回壬生町ゆうがおマラソン大会
2025年12月7日 (日)
栃木県壬生町
大会公式サイト https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2023071000012/